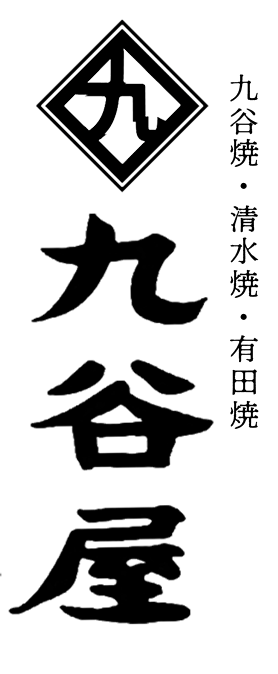九谷屋のブログへようこそ。
弊社は大正12年の創業以来、九谷焼をはじめ工芸品を専門に取り扱っている企業です。
当ブログでは焼物の魅力や、有用な情報をわかりやすく、お客様へ発信してまいります。
今回のテーマは「骨壺としてのやきもの」です。やきもの(陶磁器)を中心に、ほかの素材との違いをやさしく整理します。

■やきものの基本(磁器・陶器・炻器・素焼き)
磁器は白く緻密で、輪郭がはっきり見えます。拭き取りが早く、清潔感が出しやすいのが特徴です。
陶器はやや厚手で、光をやわらかく受け止めます。背景になじみやすく、近くでも落ち着いた表情に見えます。
炻器(せっき)は両者の中間。適度な締まりと穏やかな光の反射を持ち、扱いに迷いが少ない素材です。
素焼き(無釉・焼締)は反射が少なく、油性ペンや墨の書き入れが落ち着きます。持ち替えの際に滑りにくい点も安心材料です。
■金属・ガラス・木・樹脂とのちがい
金属は耐久性が高く、拭けばすぐ整います。一方で光の映り込みが強く、指跡が目立ちやすいことがあります。
ガラスは透明感があり軽やかです。ただし背景の映り込みが出やすく、割れへの配慮が欠かせません。
木は軽く温度変化に穏やか。家具と相性が良い反面、表面は柔らかく、経年の色変化がはっきり出ます。
樹脂は軽量で割れにくい反面、近距離では質感の差が表れやすく、静電気で埃が付きやすいことがあります。
■見え方で選ぶ
明るくきりっと見せたいなら磁器。
反射を抑え、室内光になじませたいなら陶器・炻器・素焼き。
背景が白系なら磁器が映え、木地や布の生成りには陶器・炻器・素焼きが馴染みます。
■扱いやすさで選ぶ
拭き取りの速さを重視するなら磁器。
持ち替えの安心感なら素焼き・炻器。
移動や設置が多い場合は、高台が安定した形を選ぶと負担が減ります。
■長く保つための要点
日常は乾拭きで十分です。濡れ布や研磨剤は避けます。
設置は平らな面に。台座は骨壺より一回り大きく、前後左右に指一本の余白を残します。
直射は避け、壁から1〜2cm、側面に1cmほどの空気の余白を取ると、見え方も呼吸も整います。
耐震ははがせるジェルを選ぶと、掃除や置き替えがしやすくなります。
■名入れについて(簡単な基準)
素焼きやマット地は、細めの油性ペンがのりやすく、にじみを抑えやすい面です。
書く位置は小さく一か所に。書いた後は触れず、乾きを待つだけで十分整います。
■まとめ:やきものが骨壺に向いている理由
反射が穏やかで空間になじみやすいこと。
据わりと持ち替えの設計が取りやすいこと。
手入れが増えにくく、日々の負担を抑えられること。
この三点が、やきものを骨壺の素材として選びやすくしています。
今回は、素材ごとの違いを入口に、選び方の基準を簡潔にまとめました。
お読みいただきありがとうございました。
九谷屋では、北陸の伝統工芸である九谷焼の素焼き骨壺をご用意しております。
寸法や在庫、名入れについてのご相談は、無理のない範囲でお声がけください。