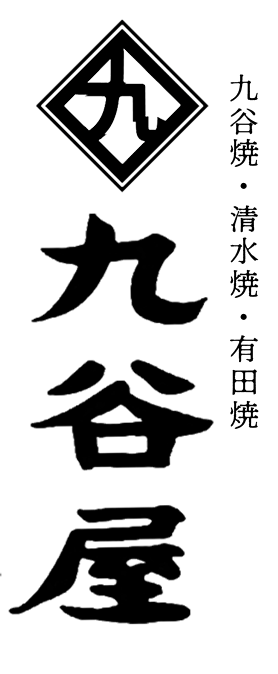九谷屋のブログへようこそ。
弊社は大正12年の創業以来、九谷焼をはじめ工芸品を専門に取り扱っている企業です。
当ブログでは焼物の魅力や、有用な情報をわかりやすく、お客様へと発信させていただきます。
今回のテーマは「中国の陶磁器と日本のやきもののちがい」です。初めての方にも読みやすく整理します。
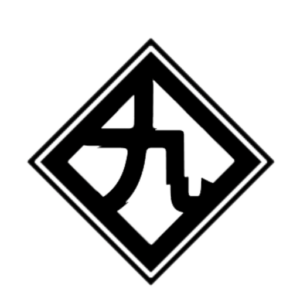
■基本の生理
やきものは大きく「陶器・磁器・炻器(せっき)」に分かれます。
中国は歴史的に磁器(白く緻密で硬い)に強く、日本は陶器(やや厚手で温かな表情)も広く根づいています。
磁器は光沢が出やすく、音が澄みます。陶器は吸水があり、肌合いがやわらかく見えます。炻器はその中間の性格です。
■歴史背景:大量生産の中国、地域多様性の日本
中国は宮廷と大市場に支えられ、景徳鎮を中心に分業と大量生産の仕組みが早く確立しました。形の統一、釉薬の均質、文様の反復に優れます。
日本は各地の窯(九谷・有田・瀬戸・信楽など)が地域の土と作風を守り、少量多品種の発展をしてきました。窯ごとの個性がはっきり残ります。
■素材と成形:白磁土の中国、多様な土の日本
中国はカオリン(高嶺土)を用いた白磁が主軸。焼き締まりが良く、薄づくりが可能で、シャープな輪郭になります。
日本は陶土の種類が多彩で、粗めの土から緻密な土まで幅広い。九谷は磁器胎も用いますが、地(土)の表情を残す設計も得意です。
■釉薬と色:青花・五彩の中国、配色の節度を重んじる日本
中国は青花(せいか/コバルトの青で描く染付)や五彩(上絵)など、色面のはっきりした装飾が得意。画面として完成度が高いのが特徴です。
日本は線と余白を重視する傾向が強く、色は主役と脇役を分けて使います。九谷焼も加飾の技法に富みますが、置かない面(余白)を残して品を整えます。
■文様の傾向:面で見せる中国、線で導く日本
中国の文様は面の構成が明快で、広い画面を一枚の絵として完成させます。
日本は線の骨格と小さな面の重ねで景色を作ることが多く、近づいても遠目でも破綻しにくいのが持ち味です。
■形と厚み:均整の中国、手取り優先の日本
中国の名窯は均整のとれた薄作りに強く、同形を精確に揃える技術が早くから発達しました。
日本は手取りの良さを重んじ、口縁の反り・肩の張り・高台の丈など、持ちやすさと据わりの設計に細かく配慮します。
■焼成と仕上がり:高温で締まる中国、多様な焼成を使い分ける日本
中国の磁器は高温焼成で緻密に締まり、薄くても強度が出ます。釉は透明感が高く、光沢がはっきりします。
日本は酸化・還元・焼締(無釉)など焼成の幅が広く、マットから強い艶まで表情が多彩。土味や焼き色を意図的に活かす作りも少なくありません。
■見た目の印象:明快な中国、やわらぐ日本
中国:白が明るく、輪郭も文様もコントラストが高い。展示映えしやすい。
日本:色も輪郭もやわらかい階調で、近距離でも遠目でも落ち着いて見えます。室内の光でもギラつきにくい仕上がりが多いです。
■扱いの違い:強度と清掃性、肌合いと馴染み
磁器中心の中国は汚れに強く、清掃が容易。薄作りでも扱える強度があります。
日本の多様な土と焼成は肌合いの変化を楽しめます。乾拭きで落ち着く表情、布・木・金属との取り合わせの幅広さが利点です。
■初心者のチェックポイント(3つだけ)
・素材:磁器(シャープ・光沢)か、陶器/炻器(温かみ・表情)か。
・文様:面で強く見せるか、線と余白で静かに見せるか。
・用途:展示的に映えさせたいか、日々の空間になじませたいか。
今回は、中国陶磁と日本のやきものを、入口の違いに絞って整理しました。
お読みいただきありがとうございました。
九谷屋では、北陸の伝統工芸である九谷焼の素焼き骨壺をはじめ、各地のやきものについてのご相談を承っております。無理のない範囲でお声がけください。