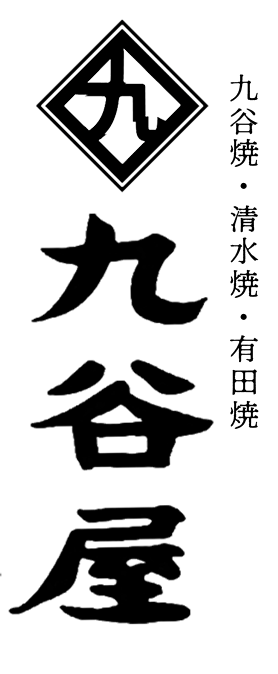九谷屋のブログへようこそ。
弊社は大正12年の創業以来、九谷焼をはじめ工芸品を専門に取り扱っている企業です。
当ブログでは焼物の魅力や、有用な情報をわかりやすく、お客様へと発信させていただきます。
今回のテーマは「日本のやきもの入門②──世界から見た評価と特徴」です。
日本の陶磁が海外で評価されてきた理由
日本のやきものは、早くから「暮らしの道具でありながら、美としても通用する」と受け止められてきました。17世紀後半、有田(伊万里)の磁器がヨーロッパに大量に渡り、王侯貴族の食卓や室内装飾を彩ります。のちに柿右衛門様式の白地に余白を生かした上絵は、ドイツやフランスの工房で研究対象となり、マイセンやシャンティイなどが意匠を学びました。日本の「白地と余白」「抑えた色の置き方」は、ヨーロッパの磁器づくりに具体的な影響を与えています。
九谷焼の評価:金襴手から近代の輸出へ
九谷焼は加飾の妙で知られます。明治以降は金襴手(きんらんで)をはじめとする華やかな作品が、国際博覧会を通じて広く紹介され、輸出が大きく伸びました。明治初期には「生産の多くが海外へ」という局面もあり、九谷という名は海外市場でも“装飾の日本”を代表する語のひとつになります。
「民藝」とスタジオ陶の橋渡し
20世紀になると、柳宗悦・濱田庄司・河井寛次郎らが唱えた民藝運動が、「用の美」を再定義しました。英国の陶芸家バーナード・リーチとの往還は、東西の陶芸観を行き来させ、手仕事の価値を世界に語る契機となります。今日もリーチ工房や各国の展覧会で、民藝の思想や日本の陶が紹介され続けています。
技と人への評価―「人間国宝」という考え方
日本には、重要無形文化財の保持者(いわゆる人間国宝)を公に認定し、技術そのものを文化として守る仕組みがあります。陶芸もその対象で、素材の扱い・焼成の見極め・加飾の所作など、人が持つ熟練を社会全体で継承していく考え方です。海外でもこの枠組みは注目され、日本の“技中心”の保存思想は、評価の土台になっています。
海外の美術館・市場で見られる“日本らしさ”
海外の収蔵・展示では、次の視点がしばしば語られます。
-
余白と抑制:白地を生かし、必要な色だけを置く(柿右衛門に典型)。ディテールより間(ま)が景色を決める発想。
-
線と骨格:染付の細線、九谷の線描。線が視線の通り道を作る。
-
土と火の表情:備前・信楽などの焼締。釉ではなく土肌と焼成の偶然を尊ぶ見方。
いずれも、派手さではなく節度に価値を見いだす評価軸です。これは、日常の道具であり続けた日本の陶磁の性格と響き合っています。
今回は、日本のやきものが世界でどう見られてきたかを手短に整理し、日常の実践へつなげました。
お読みいただきありがとうございました。
九谷屋では、北陸地方を代表する伝統工芸・九谷焼の素焼き骨壺をご用意しています。
在庫や寸法、名入れについてのご相談は、どうぞ無理のない範囲でお声がけください。