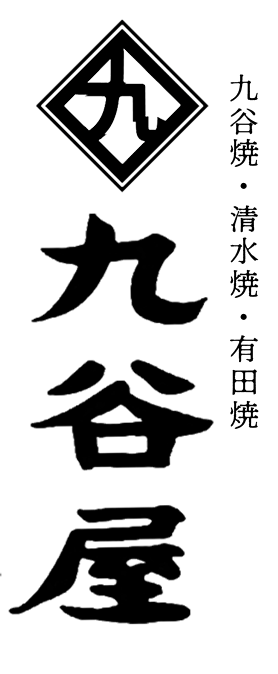九谷屋のブログへようこそ。
弊社は大正12年の創業以来、九谷焼をはじめ工芸品を専門に取り扱っている企業です。
当ブログでは焼物の魅力や、有用な情報をわかりやすく、お客様へと発信させていただきます。
今回のテーマは「日本のやきもの入門──九谷から始める基礎の見方」です。

■まず押さえたい基本用語
やきものは大きく「土(素地)」「釉薬(うわぐすり)」「焼成」の三つで決まります。
釉薬をかけて焼くと、表面はつるりとし、汚れに強くなります。
釉薬をかけない焼締(しめやき/素焼き寄りの状態)は、光がやわらかく、手触りが温かいのが特徴です。
模様を焼いた後に色をのせるのが上絵付け、青一色で描くのが染付です。
■九谷焼の基礎:色よりも「節度」と「線」
九谷焼は上絵付けの名手ですが、色の多さを競うものではありません。
主役の色を一つ、支える色を一つ。線は細く、面は小さく。置かない余白を残すと、落ち着きが出ます。
骨壺まわりに使うなら、派手さを抑えた九谷が向きます。遺影や花立と並べても視線が散りません。
■素焼き(焼締)のよさ:骨壺に向く理由
素焼きは釉薬を使わないため、光が強く跳ね返りません。部屋の明かりや日中の光でもぎらつかず、静かに見えます。
手触りはさらり。持ち替えるときに滑りにくく、安心があります。
名入れ(日付・お名前など)を書き入れる面としても適しています。油性ペンや墨が落ち着きやすく、にじみを抑えやすいからです。
■有田・伊万里(佐賀):白の張りと染付の明るさ
白磁の凛とした白、染付の青い線がわかりやすい焼物です。
骨壺の周辺をすっきり見せたい方に向きます。背景が木地でも白が濁らず、香立や花立の位置決めがしやすいのが利点です。
■備前・信楽(岡山・滋賀):焼締の力強さと土味
どちらも無釉の焼締(しめやき)。光をやわらかく受け、落ち着いて見えます。
骨壺の台座は一回り大きめに。前後左右に指一本の余白を取ると、土味の表情がきれいに出ます。
壁から1〜2cm離すと通気が保て、影も浅く見えます。
■萩・唐津(山口・佐賀):やわらぐ肌と余白の景色
萩は使うほどにやさしい艶が育ちます。唐津は面の揺らぎが穏やかです。
祈りの場で「派手さはいらない」という方には良い選択肢。
敷布は薄い生成りが無難。輪郭が見やすく、所作の邪魔をしません。
■瀬戸・美濃・京焼(愛知・岐阜・京都):日常に寄り添う品
瀬戸・美濃は実用の安定感、京焼は意匠の品が持ち味です。
骨壺まわりでは、敷板や小物の“やり過ぎ”を避けるだけで十分きれいに整います。
照明は正面からではなく、やや上から。影が浅くなり、落ち着いて見えます。
今回は、九谷焼と素焼きを起点に、主要な焼物の特徴と骨壺まわりでの生かし方をやさしく整理しました。
お読みいただきありがとうございました。
九谷屋では、北陸の伝統工芸である九谷焼の素焼き骨壺をご用意しています。
在庫や寸法、名入れのご相談は、どうぞ無理のない範囲でお声がけください。