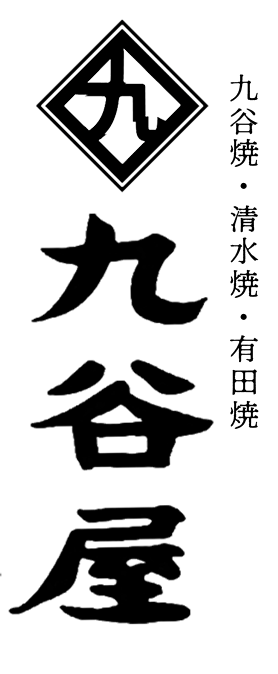九谷屋のブログへようこそ。
弊社は大正12年の創業以来、九谷焼をはじめ工芸品を専門に取り扱う企業です。
当ブログでは焼物の魅力や、有用な情報をわかりやすく、お客様へと発信させていただきます。
今回のテーマは「九谷焼と素焼き──骨壺にふさわしい静けさ」です。

■九谷焼とは何か:線と面、そして“間”の美
九谷焼は、加飾の技(上絵付け)に強みを持つやきものです。
筆で引いた線が図案の骨格をつくり、面が色の体温を運ぶ。色と色のあいだに残される“間”が、器の呼吸を決めます。
九谷五彩(赤・青・黄・紫・緑)で知られますが、色を重ねることだけが九谷の本質ではありません。どこに置き、どこに置かないか。その節度こそが、静かな品格を生みます。
九谷のつくり手は、形・線・地(素地や釉の白)を三位一体で見ます。
形は手の収まりを、線は視線の通り道を、地は余白の空気を担います。
骨壺においても同じ考えが働きます。置き場所、向き、周囲の道具との距離。どれもが“間取り”です。九谷の設計思想は、祈りの所作に静かに寄り添います。
■素焼きという選択:釉薬をかけない“呼吸する肌”
素焼き(焼締め)は、釉薬をかけずに焼き締めた状態です。
表面に微細な凹凸が残り、光をやわらかく受け止めます。強い反射がないため、居室・仏間・本棚、どの背景にも溶け込みます。
手に触れると、わずかな温度が伝わります。冷たさよりも“静かな温かさ”。手元供養の場にふさわしい理由のひとつです。
素焼きの肌は、油性ペンや墨の定着が穏やかです。
お名前や日付を、ひと言だけ添える。必要があれば、後からそっと加える。にじみを抑える書き方、乾き待ちの目安、定着の工夫――こうした“実務”が、素焼きでは無理なく行えます。
名入れを大きく飾らないで済むことは、祈りの時間を乱さないことにもつながります。
■骨壺に向く理由①:光をおさえる“静かな景色”
祈りの場では、視線が散らないことが大切です。
素焼きは光沢を抑え、輪郭をふわりと立ち上げます。遺影や花立・香立と並んだとき、骨壺だけが主張することはありません。
背景が白でも木地でも、派手なコントラストになりにくい。結果として、正面を向き、手を合わせる動きが保たれます。
加飾を控えた九谷の上絵は、その静けさをさらに支えます。
線を細く、面を小さく。角(口縁・肩・高台)に触れたり、面積を広げすぎたりしない。わずかな刷毛目や線金が、拍子木のように「ここで止まる」目印になります。
“見せる”ための装飾ではなく、“祈る”ための節度。九谷焼の技は、ここで本領を発揮します。
■骨壺に向く理由②:触れる所作にかなう形
形は触覚の設計図です。
肩の張りが手の置き場を生み、口縁の反りが指先の安全を守ります。高台の丈は、持ち上げと据え置きの安定を両立します。
素焼きのわずかな摩擦が、持ち替えのときに頼りになります。滑らない。驚かせない。日々の扱いで、これほど心強い性質はありません。
置き方にも、無理のない基準があります。
座位なら台座上面が床から80〜100cm、床座なら40〜60cm。
遺影の下端と骨壺の上端のあいだに、指二〜三本の余白。
台座は骨壺より一回り大きく、前後左右に指一本の余白。どれも“所作が続く”ための寸法です。
■骨壺に向く理由③:名入れが“言い過ぎない”
名入れや日付は、必要十分であることが大切です。
素焼きは、細い線でもしっかり読み取れる落ち着いた面(おもて)を持ちます。
正面の片側に小さく、あるいは背面にそっと。縦横は、祈るときの視線で決めます。
書いた直後は触れず、乾きを待つ。必要なら簡易の定着処理をする。控えめな段取りで、過不足なく整います。
■骨壺に向く理由④:経年の表情が“古びない”
素焼きは、乾拭きの積み重ねで、ほんのりとした艶が育ちます。
摩耗ではなく“落ち着き”。時間が作る表情は、祈りの場に不思議な安心をもたらします。
濡れ布・研磨剤・強い香りは避け、やわらかな布で上から下へ。やることを少なくするほど、品が長く保たれます。
■九谷焼×素焼きの相性:線・面・地の“三和”
九谷の線は、素焼きの地で音量が下がり、余韻だけが残ります。
面(色)は、指三本幅を超えない。角に触れたら次は触れない面を残す。
この控えめな約束事が、骨壺の表情を整えます。加飾が働きすぎないぶん、形と余白が先に立つ。祈りの場にふさわしい“静かな三和”です。
■置き場所と向き:半歩の調整で“祈りやすさ”は変わる
正面は、手を合わせる人の位置へまっすぐ。
遺影があれば中心を合わせ、香立・花立とゆるい三角形をつくります。
直射を避け、壁から1〜2cm、側面に1cmほどの通気を残す。耐震は外せるジェルで。安全と清掃が両立します。
迷ったら、正面に戻す。角度は“半歩”だけ。賑やかさを避ける最短の方法です。
■季節への配慮:湿度と風の“やり過ごし方”
梅雨時は、壁際の空気が滞りやすくなります。
背面と側面の余白で、むりなくやり過ごします。
冬は加湿器の蒸気を直接当てない。結露の出やすい窓際では、位置を半歩だけ離す。
置き替えの前に一枚の写真を。戻すとき、安心の設計図になります。
■最後に
九谷焼の節度と、素焼きの静かな肌は、お骨が過ごしていく静かな時間を乱しません。
無地であること。書けること。光を抑えること。持ち替えやすいこと。毎日の手当が少なくて済むこと。
骨壺は、“大切な方の存在した証を、確かに残していく道具のひとつ”です。
どうかよき選択ができますことを、心よりお祈り申し上げます。
今回は、九谷焼と素焼きの特徴が、骨壺という役目にどのように重なるかをお伝えしました。
お読みいただきありがとうございました。
九谷屋では、北陸地方を代表する伝統工芸である九谷焼の素焼き骨壺をご提供しております。
在庫やサイズ、書き入れについてのご相談は、どうぞ無理のない範囲でお声がけください。