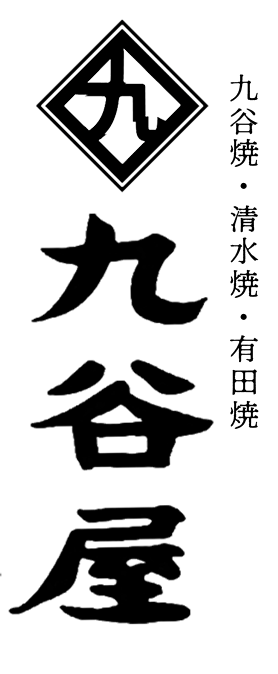こんにちは。
九谷屋スタッフブログへようこそ。
本日のテーマは九谷焼の特徴の一つ、「九谷五彩(くたにごさい)」でございます。派手というより、近づくほど奥行きが増す不思議な色あい。
本記事では、五つの色の役割を、むずかしい専門用語を避けてわかりやすく整理いたします。
※本文の前に
実際の色合いや風合いは、ぜひ実物で確かめていただくのが安心です。
九谷屋公式サイトにて各種の九谷焼素焼き骨壺をご覧いただけます。どうぞこちらもあわせてご参照ください。
👉 九谷屋公式サイトはこちら
1.九谷五彩とは何か
九谷五彩とは、九谷焼で伝統的に用いられる緑・黄・紫・紺青・赤の五色のことです。色そのものが強いのではなく、釉薬の上に色を重ね焼きすることで透け感と深みが生まれ、遠目には静かに、近づくと豊かに見えるのが特徴でございます。
同じ「緑」でも工房や作家によって明度や質感に幅があり、照明や時間帯で印象が変わります。画像だけで決めず、できれば実物を離れて一度、近づいて一度ご覧になると、奥行きの理由が自然に伝わってまいります。
2.五つの色の役割(色名だけでなく“見え方”で理解)
五彩は、互いに引き立て合うための配置と重なりで成り立っています。色の“意味”を断定しすぎず、見え方の性格で捉えると選びやすくなります。
-
緑:最も頼もしい“土台”の色。面で使っても目が疲れにくく、葉や唐草と相性が良い緑は、空間全体を落ち着かせます。
-
黄:光を足す“ひかり役”。点や縁取りに少量入ると、器がふっと明るく見えます。広い面積だと元気に映るため、骨壺では控えめが上品です。
-
紫:影と余韻をつくる“奥行き役”。緑や紺青の近くに入ると重なりが深く見え、厳かな雰囲気が整います。
-
紺青:画面を引き締める“輪郭役”。模様の線や小さな面で使うと、構図が凛として見えます。夜の電球色でも色ぶれが少ないのが利点です。
-
赤:視線をやさしく集める“焦点役”。細い線や小さな面で使うと、温度感がほんの少し上がり、写真や花の色とも馴染みます。
五彩は主役を一色に決めるものではなく、調和のための配合でございます。どの色が多いか、どこに置かれているかで印象が変わりますので、全体のバランスでお選びください。
3.どうやって色がつくのか(上絵付けのしくみ/染付との違い)
九谷五彩は、器を本焼きした後に色をのせてもう一度焼く上絵付けで表現されます。釉(うわぐすり)の“上”に色が乗るため、色が光を含んで見えるのが特長です。
これに対し、焼成前の素地に藍色の絵具をしみ込ませてから透明釉をかけて焼くのが下絵付け(染付)。線や文様がすっきり見え、青の濃淡に独特の味わいが出ます。下絵付けの基礎を先に知っておくと、上絵の発色や艶との違いがより分かりやすく感じられるでしょう(**「下絵付け(染付)の基礎はこちら」**といった内部リンクの挿入をおすすめいたします)。
4.骨壺での見え方と選び方(ご自宅の光・距離・置き場所)
骨壺は、日々の視線がもっとも集まる器のひとつです。色そのものより置く環境との相性で判断されると、後悔が少なくなります。
光の質
昼の拡散光では緑・紫の重なりが穏やかに、夜の電球色では赤・黄があたたかく見えやすい傾向がございます。お部屋で手を合わせる時間帯を思い浮かべながらご確認ください。
見る距離
約1メートル離れて全体の静けさを、30センチほどで重なりの細部を。それぞれ一度ずつご覧いただくと、色の“働き”が分かりやすくなります。
置き場所
直射日光やエアコン直下は、反射や乾燥で印象が変わりやすい環境です。低く安定した棚に、滑り止めや布を一枚添えるだけで、見え方が落ち着きます。
色の配分
花の色数が多い季節は、器側の赤や黄を控えめに。冬や色が少ない時季は、赤・緑・紺青の小さな面が空間の温度を支えてくれます。**“主役は季節で譲り合う”**と覚えておかれると、長く馴染みます。
5.よくある疑問(褪色・金彩・お手入れの基本)
色は褪せますか?
通常の室内環境では急に褪せることは少ない印象です。ただし、直射日光と高温は避けましょう。窓辺で長時間の直射が続くと、艶や印象が変わる場合があります。
金彩は目立ちますか?
金彩は“縁取り”や“点”に使われ、光をやわらかく拾う役として働きます。強い照明や直射が当たると反射が気になることもあるため、置き場所の光を見て判断されると安心です。
お手入れは?
乾いた柔らかい布でそっと乾拭きが基本でございます。研磨剤や強い洗剤は避けてください。埃が気になる場合は、やわらかい刷毛で払ってから布で整えると、表面を傷つけにくいです。環境管理(直射・結露・転倒防止)を優先されると、きれいな状態を長く保てます。
6.まとめ
九谷五彩は、緑・黄・紫・紺青・赤の五色が、重なりと配置で静かな調和をつくる技法でございます。強い色を“足す”というより、場に“馴染ませる”感覚でお選びになると、ご自宅の光や季節の花と自然に溶け合います。どの選択にも唯一の正解はございません。大切なのは、ご家族が納得できるかたちであること。本記事が、そのための静かな道しるべになれば幸いです。ご不安な点は、どうぞ遠慮なくおたずねください。
九谷屋では、北陸地方を代表する伝統工芸品である九谷焼の素焼き骨壺をご提供しております。
宮内庁にも携わった作家の形づくる、良質で安価な一品をぜひ一度ご覧ください。