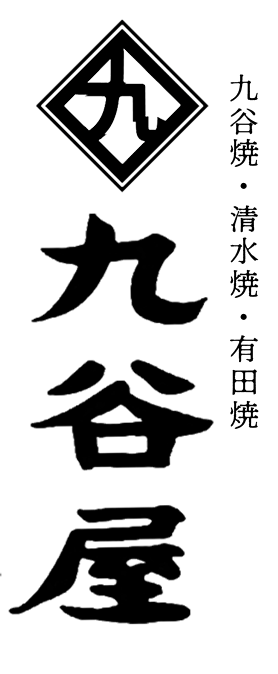九谷焼のブログへようこそ。
弊社は大正12年の創業以来、九谷焼をはじめ工芸品を専門に取り扱ってまいりました。
当ブログでは、伝統が息づく焼物の魅力や、日々の暮らしに寄り添う知識をわかりやすくお伝えしています。
今回のテーマは、「九谷焼に見る“素焼き”技術の機能美」です。
■“素焼き”という選択
焼物の世界で「素焼き」という言葉を聞くと、多くの方は少し地味な印象を抱かれるかもしれません。
けれども、九谷焼の素焼きには、目立たないながらも、確かな存在感と静かな美しさが宿っています。
素焼きとは、釉薬をかけずに土そのものを低温で焼き締める、いわば“土の呼吸”をそのまま残した器づくりです。
■多孔質がもたらす、やさしい働き
素焼きの最大の特徴は、多孔質構造です。
無数の微細な孔が、空気や水分の通り道となり、器に「呼吸する力」を与えています。
九谷焼の骨壺にこの技法が生きるのは偶然ではありません。
日本の湿度や温度の変化に寄り添い、中に納めたものを、湿気からも乾きすぎからも守る。
多孔質の素地は、まるで見えない手で、静かに中身を包み込んでいるようです。
■描き手と土の対話
素焼きの素地は、絵付けをする職人にとっても、特別な感触をもたらします。
釉薬に覆われていない分、顔料や墨がじんわりと土に染み込み、
筆の運びや色の濃淡までも、素直に受け止めてくれる。
九谷五彩の鮮やかさが、時に大胆に、時に静謐に、素焼きの肌に現れるのは、
この“土との対話”があるからです。
仕上がった器には、決して工業製品では得られない、作り手の呼吸が刻まれています。
■暮らしに息づく素焼きの美
素焼きの九谷焼は、見た目の華やかさよりも、
触れたときの温もり、静かな佇まいにこそ、真価が宿るものです。
ひとつ手にとってみると、不思議と手になじみ、
土そのものの温度や重みが心地よく伝わってきます。
それは400年にわたり受け継がれた“日々の道具”としての知恵であり、
同時に、現代の暮らしにもしっくり溶け込む、工芸の根っこの力です。
■“下地”で終わらない、素焼きの品格
私たちは、素焼きを単なる途中段階とは考えていません。
素焼きには、土の声を聴き、作り手の手業が正直に伝わる“完成形”としての美しさがある。
華美な装飾がなくとも、静かな気配を放ち、
使うほどに、見るほどに、じわりと心に沁みる存在――
それが、九谷焼の素焼きの機能美なのだと思います。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
九谷屋では、伝統と新しさの両方を受け継ぐ九谷焼の素焼き骨壺をはじめ、
さまざまな焼物をご紹介しています。
ご興味がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。