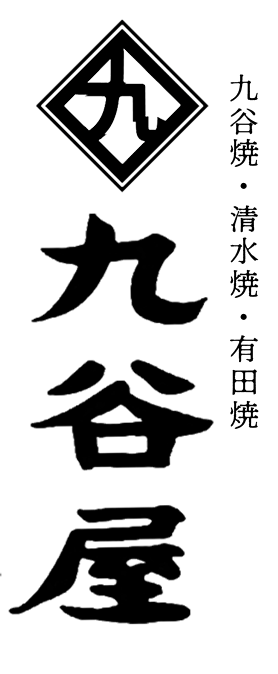九谷屋のブログへようこそ。
弊社は大正12年の創業以来、九谷焼をはじめ工芸品を専門に取り扱っている企業です。
当ブログでは焼物の魅力や、有用な情報をわかりやすく、お客様へと発信させていただきます。
前回の記事では、改葬やお墓参りの際、あるいは手元供養をされている場合など、骨壺の状態を確認する機会があることをお伝えいたしました。
今回は、そうした際に行う「骨壺の表面のお手入れ方法」について、素材別に詳しくご紹介いたします。
これを読んでいただくことで、骨壺を美しく保ち、故人への想いを長く大切にするための具体的な方法がわかります。
ご参考いただければ幸いです。
★陶器(素焼き・釉薬あり)の骨壺のお手入れ
陶器の骨壺は、広く用いられている一般的な素材です。
■お手入れ方法
・普段のお手入れ
柔らかい布やハタキで、表面のホコリを優しく払います。乾拭きを基本とし、必要に応じて軽く湿らせた布で拭き、その後すぐに乾拭きを行います。
・汚れが目立つ場合
ごく薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き、仕上げに水拭きと乾拭きを行います。
▲ポイント
・素焼きの骨壺は水分を吸収しやすいため、水濡れに注意しましょう。
・釉薬仕上げのものは、表面のヒビに水分が入り込まないよう配慮してください。
★金属製(ステンレス・真鍮・アルミなど)の骨壺のお手入れ
金属製の骨壺は耐久性が高く、割れる心配がありませんが、サビやくすみが発生する場合がございます。
■お手入れ方法
・普段のお手入れ
柔らかい布で乾拭きし、表面の汚れを取り除きます。指紋やくすみが気になる場合は、メガネ拭きなどの柔らかい布で優しく拭き取ります。
・くすみやサビが見られる場合
素材ごとにわかりやすくご説明します。
ステンレス製の場合、少量の食用油を布に含ませて拭くと、光沢が戻ります。
真鍮製は、専用のクリーナーを使用することで輝きを保つことができます。
アルミ製は、重曹を水に溶かしたものを布に含ませ、優しく磨く方法が適しています。
▲ポイント
・水分が残るとサビの原因となるため、必ず乾拭きを行いましょう。
・研磨剤やスチールウールなどの硬い素材でこするのはキズや傷みの原因となります。
★ガラス製の骨壺のお手入れ
ガラス製の骨壺は、透明感のある美しいデザインが特徴ですが、指紋やホコリが目立ちやすい素材でもあります。
■お手入れ方法
・普段のお手入れ
柔らかい布やメガネ拭きを使用し、表面を乾拭きします。指紋が気になる場合は、眼鏡用クリーナーやガラス用クリーナーを用いると良いでしょう。
・くもりや水アカが気になる場合
お酢を水で薄めたものを布に含ませ、優しく拭きます。次にガラスクリーナーを使用し、拭き跡が残らないよう乾拭きを行います。
▲ポイント
・こするときもやさしく。傷がつくと割れやすくなります。
・水洗いした場合は、十分に乾燥させてから安置しましょう。
★木製の骨壺のお手入れ
木製の骨壺は、温かみのある風合いが魅力ですが、湿気や虫害に注意が必要な素材です。
■お手入れ方法
・普段のお手入れ
ハタキや柔らかい布でホコリを払い落とします。
・汚れが気になる場合
少量の木材用オイル(オリーブオイルなど)を布につけ、優しく拭きます。
▲ポイント
・水拭きは避けましょう。湿気を吸収すると変形やカビの原因となります。
・虫害を防ぐため、ヒノキチップなど防虫効果のあるものを近くに置くことをおすすめします。
★石製(大理石・御影石)の骨壺のお手入れ
石の骨壺は、重厚感と高い耐久性を誇りますが、表面の汚れが目立ちやすいという特徴があります。
■お手入れ方法
・普段のお手入れ
柔らかい布で乾拭きします。
・水アカや汚れが目立つ場合
中性洗剤を薄めた水で拭き、仕上げに乾拭きを行います。
ポイント
・酸性洗剤の使用は避けてください。石材が劣化する原因となります。
・持ち運びは慎重に。重さがあるため、落とすと破損の恐れがあります。
■まとめ
骨壺の表面のお手入れは、素材ごとに適した方法で行うことが重要です。
・陶器製:水分に注意しながら布で拭く。
・金属製:乾拭きを基本とし、サビには食用油や専用クリーナーを使用。
・ガラス製:指紋が目立つため、専用クリーナーで拭く。
・木製:湿気を避け、乾拭きが基本。
・石製:酸性洗剤を避け、中性洗剤でお手入れする。
適切なお手入れで、お客様方の骨壺が状態を保ち、末永く丈夫であられることを願っております。
いかがでしたでしょうか。
次回は、「骨壺の内部のお手入れ方法」について詳しくご紹介いたします。
お読みいただきありがとうございました。
九谷屋では、北陸地方を代表する伝統工芸品である九谷焼の素焼き骨壺をご提供しております。 宮内庁にも携わった作家の形づくる、良質で安価な一品をぜひ一度ご覧ください。