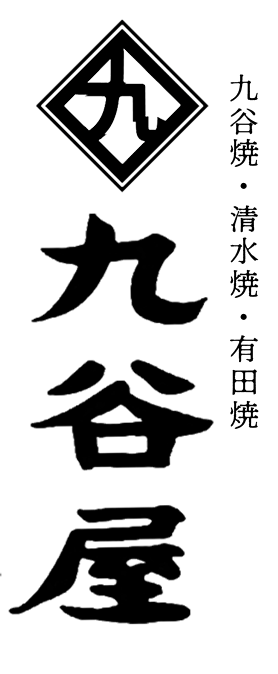九谷屋のブログへようこそ。
弊社は大正12年の創業以来、九谷焼をはじめ工芸品を専門に取り扱っている企業です。
当ブログでは焼物の魅力や、有用な情報をわかりやすく、お客様へと発信させていただきます。
今回のテーマは「骨壺の代表的な素材」です。
■代表的な素材一覧
骨壺の素材には大別して以下の5種類があります。
①陶器
②金属
③ガラス
④木材
⑤石材
以下、ひとつずつ特色をご説明します。
①陶器
骨壺の最も一般的な材質とされています。
陶磁器は粘土を主に使用した焼物で、通気性によるご遺骨の保存性や経年劣化の少なさが特徴です
また、デザインや質感に気持ちを込めることができ、総合的に最も選ばれやすいと素材いえます。
製法の違いや釉薬の使用によって多様な色形をとることが可能で、デザインに主眼を置いて選ぶ場合も最適の選択肢です。
九谷焼、美濃焼、有田焼、伊万里焼など産地によって個性があり、素焼きなど製法によっても質が多彩です。
唯一、割れやすいのが注意点です。
持ち運びでの落下や安置場所には気をつけたほうがよいでしょう。
②金属
主に真鍮や銅、アルミニウムが使用されます。
通気性はありませんが、密閉性が高いため、乾いた場所で納骨すれば、防湿性に優れ、カビや水の侵入を効率的に防ぐことができます。
また、耐久性に優れ、万が一落としたり倒したりしても割れる心配は、ほぼありません。
デザイン面でもバリエーションが多く、モダンでスタイリッシュな姿形を作ることができ、手元供養などで特に人気が高い素材です。
ただし、素材によってはサビのメンテナンスが必要で手がかかったり、熱伝導性が高いため直射日光に当てると劣化や破損の原因になりやすいのが短所です。
③ガラス
ガラス骨壺には2種類の区分と特徴があります。
まず、透明または半透明で内部が見えるタイプ。
これはご遺骨を常に確認することができる特色を持ちます。
次に、内部が見えないもの。
これは主に染料やラメ、形態など美しくユニークなデザイン性を持ち、故人や亡くなったペットの思い出を骨壺に見出される需要が多くあります。
どちらのタイプも手元供養に人気です。
衝撃に弱く、強度はあまりありません。
取り扱いや安置場所には細心の注意が必要です。
④木材
木製の骨壺は、自然素材のため温かみを感じられます。
また環境に優しく、土に還るため自然葬に向いた素材といえます。
彫刻やペイントが可能なので、デザインにもバラエティがあります。
軽量で持ち運びがしやすいのも長所です。
ただし湿気や虫害に弱く、高温多湿の日本では長期間の保管には不向きです。
通常の供養の場合、手元供養でも骨壺を頻繁に交換する予定がない場合は他の素材を検討するのが無難でしょう。
⑤石材
石の骨壺は陶磁器と同じく古く、古代から使用されてきました。
大理石、御影石などの石材は重厚感と存在感、そして高級感のある骨壺を形作ります。
厳かな雰囲気を持つだけでなく、風化や破損に耐え、数世代にわたって遺骨を保護できます。
耐久性も高いため、手元供養での頻繁な取り扱いや置き場所の選定にも安心感があります。
短所としては、非常に重いため、6寸や7寸サイズの骨壺は持ち運びにくいことが挙げられます。
また、値段の幅はありますが、他の素材に比べて高価なものが多く、予算など事前の考慮が要るかもしれません。
以上、今回は骨壺の代表的な素材5選をご紹介いたしました。
お読みいただきありがとうございました。
九谷屋では、北陸地方を代表する伝統工芸品である九谷焼の素焼き骨壺をご提供しております。
宮内庁にも携わった作家の形づくる、良質で安価な一品をぜひ一度ご覧になっていただければ幸いです。