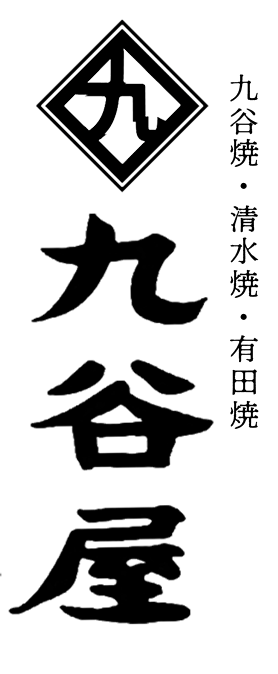九谷屋のブログへようこそ。
弊社は大正12年創業以来、北陸・石川の伝統工芸である九谷焼を長年にわたり扱ってまいりました。今回は、その九谷焼がどのような歴史を歩み、いかにして日本を代表する陶磁器となったのか、その軌跡をご紹介します。
■江戸時代:古九谷の誕生(1655年頃)
江戸時代、加賀の山あいでひっそりと発見された陶石。ここから物語は始まります。時は1655年、藩主・前田利治の命によって窯が築かれ、後藤才次郎が有田で学んだ技を活かして最初の九谷焼を生み出しました。
この初期作品は、後に「古九谷(こくたに)」と呼ばれます。九谷五彩――緑、黄、紫、紺青、赤――で描かれた力強い絵付けは、まさに北陸の冬に華を添える存在だったと言われています。その鮮烈な色彩と大胆な構図は、いまなお多くの陶芸愛好家を魅了しています。
ところが、古九谷の窯はわずか半世紀ほどで突然幕を閉じます。途絶えた理由は今なおはっきりしませんが、その美しい作品は“幻のやきもの”として人々の憧れとなりました。
■幕末〜江戸後期:再興九谷の誕生(19世紀)
時代は流れ、19世紀になると九谷焼はふたたび息を吹き返します。加賀藩の支援で京都から青木木米を招き、吉田屋、宮本屋、永楽など新たな窯が開かれました。再興九谷の時代です。ここで生まれたのが、繊細な赤絵細描や、金襴手(きんらんで)と呼ばれる豪華絢爛な金彩の装飾。技術と美が融合し、芸術性がいっそう高まりました。
■明治以降:国際性と技法の深化
明治時代に入ると、九谷焼は「ジャパンクタニ」として海を渡ります。パリ万博やウィーン万博で世界にその名を知らしめ、鮮やかな絵付けと独特の美意識は多くの人々の心をとらえました。日本独自の工芸として、国内外に誇れるブランドへと成長したのです。
■現代へ:伝統を生かし続ける九谷焼
そして現代。九谷焼は伝統技法を守りつつ、新しい表現にも挑戦し続けています。骨壺や花器、日常の食器としてだけでなく、現代アートとしても評価され、さまざまな作家が唯一無二の作品を世に送り出しています。ひとつひとつ手作りで生まれる九谷焼は、どこか懐かしく、温もりに満ちています。それはきっと、400年の歴史が積み重ねた“人の手の記憶”が、器のなかに息づいているからなのかもしれません。
■まとめ
古九谷(1655–1730頃):五彩絵付けによる大胆で鮮やかな表現。
再興九谷(19世紀):赤絵・金襴手技術の完成と世界への輸出。
近代以降:技の深化と文化財指定による正統性の確立。
現代:伝統と実用性を持って、新たな表現へと開かれ続けています。
九谷焼は、単なる工芸品にとどまらず、時代ごとの暮らしや祈り、そして作り手の誇りを映し出す存在です。その豊かな色彩と、手仕事の温かさを、これからも皆さまの日々にお届けできれば幸いです。
お読みいただき、ありがとうございました。