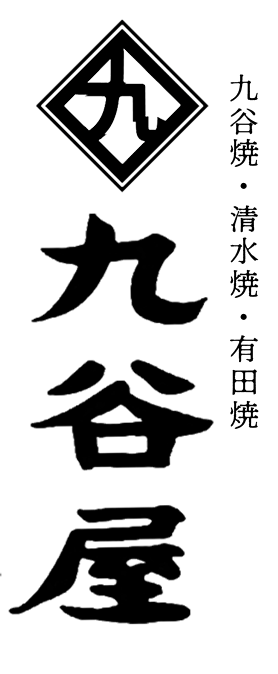九谷焼のブログへようこそ。
弊社は大正12年の創業以来、九谷焼をはじめ工芸品の世界に身を置いてまいりました。
当ブログでは、焼物の伝統、その静かな佇まいに潜む深い技術や心を、できるだけわかりやすくお伝えしています。
本日のテーマは、「九谷焼における『染付』技法──素焼き素地への呉須絵付け」です。
■藍色が滲む、“下絵付け”の美
九谷焼といえば、華やかな色絵を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、その基礎には“染付”と呼ばれる、ひと色だけの世界が広がっています。
素焼きの素地に、呉須という藍色の顔料で筆を走らせるこの仕事は、一見控えめですが、静かで力強い美しさを持っています。
下絵付けの藍は、色数こそ限られますが、線の濃淡や筆致ひとつで驚くほど豊かな表情を見せてくれます。
■素焼き素地と呉須、一期一会の対話
染付の難しさは、素焼きの素地と顔料の相性にあります。
焼き上がった素地は、微細な凹凸と多孔質の手ざわり。そこに呉須がじんわりとしみこみ、筆の運びやためらい、ほんのわずかな力加減までも、素直に映し出されます。
一度描いた線は修正がききません。描き手の息づかいや一瞬の集中が、そのまま“景色”として器に残るのです。
この“消しのきかない美”こそが、染付の凛とした佇まいの理由なのかもしれません。
■職人の心が宿る、藍の世界
藍一色で世界を表現する染付には、熟練の職人の“手の記憶”が宿ります。
細やかな線で骨組みを描き、太筆でゆっくり色を落とし込み、乾きとにじみの加減を計算しながら仕上げていく――。
単調に見える藍の色にも、重ね方や筆の角度で深いグラデーションが生まれ、見るほどに味わいが増してきます。
染付は、目立つ華やかさはありません。けれど、その静けさと奥行き、にじむような陰影があるからこそ、
毎日の暮らしのなかでそっと寄り添い、長く愛され続けているのだと思います。
■歴史と現代、そして九谷焼ならではの染付
染付のルーツは中国・景徳鎮の青花にさかのぼりますが、九谷焼の染付は日本の土や水、作り手の感性のなかで独自に育ってきました。
しっとりとした九谷土の手ざわり、伝統の文様、そして現代の器としての形。
そのすべてが、藍色の線に託されて受け継がれています。
今では、染付の器はモダンな食卓にもよく似合い、シンプルな中に静かな個性が光ります。
九谷焼の染付は、色絵の華やかさとは異なる、“余白の美”や“間”の味わいを教えてくれる存在です。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
九谷屋では、伝統と新しさが溶けあう九谷焼の染付の器も多数ご紹介しています。
日々の暮らしに、しずかに寄り添う藍色の美を、ぜひ手にとってご覧ください。